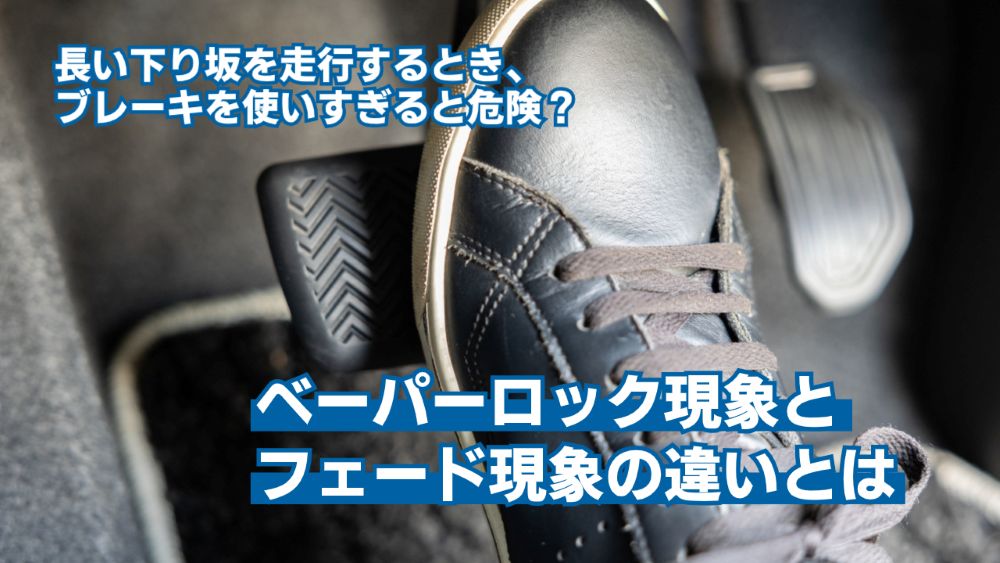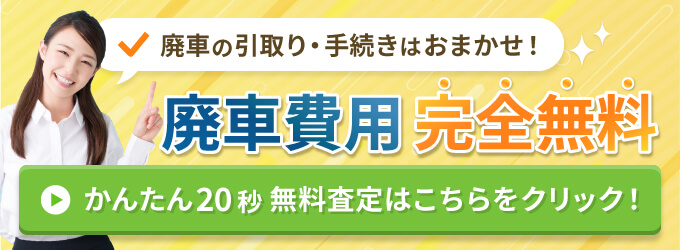ベーパーロック現象とフェード現象とは、 どちらも車の運転操作時に発生する現象のことです。車の基本的な運転操作というと【走る・曲がる・止まる】となりますが、今回解説する二つの現象はどちらも、ブレーキペダルを踏んで【止まる】操作をしようとした際に発生します。
こちらの記事では、ベーパーロック現象とフェード現象について、それぞれどんな時に起こり、どんな状態になるのか詳しく解説します。
ベーパーロック現象・フェード現象とは
ベーパーロック現象・フェード現象は、車を減速または停止させるためにドライバーがブレーキペダルを踏んで、フットブレーキ操作を行った時、もしくは頻繁にブレーキを踏み続けてフットブレーキを酷使した時に起こる現象のことです。
まずは二つの現象について解説する前に、ブレーキの構造や仕組みについて解説します。
フットブレーキの仕組み
走行している車を減速もしくは停止させるためにフットブレーキを使うと、どのような仕組みで制動力がかかるのかご存知でしょうか。
フットブレーキは、ドライバーが足元のブレーキペダルを踏むと、ブレーキ機構の内部にあるピストンが押し出され、ブレーキオイル(ブレーキフルードとも呼ばれる)がホースを通ってタイヤ周辺へ巡ります。このピストンの働きによって圧力がかかって押されたブレーキパッドが、回転しているディスクローターに強く押し付けられることで摩擦が発生し、その摩擦抵抗によって回転が抑制されて車に制動力がかかる仕組みとなっています。
ベーパーロック現象とは?

では、ベーパーロック現象(vaporは蒸気、lockは固定や詰まるといった意味)について解説します。
ベーパーロック現象は、前述したブレーキの仕組みでも解説したようにブレーキペダルを踏むことでタイヤ周辺へ巡ブレーキオイルが沸騰してしまい、オイル内に気泡が発生したことでブレーキが効きづらくなるといった現象のことです。
そもそものブレーキオイルは、摩擦熱で高温になることを前提としているため耐熱温度は200度を超えています。そのため本来であれば、沸騰することはほとんどありません。しかし、ブレーキオイルは吸湿力が高く水分を含みやすいという特性をもっていて、気温差等で発生する結露等の水分を含んだブレーキオイルの沸点は、従来より低くなってしまうことから沸騰しやすくなっているのです。
ブレーキオイルが摩擦熱によって沸騰すると、ブレーキホース内にぶくぶくと気泡が発生してしまいます。その気泡がエアポケットとなって油圧システムによって発生させた圧力を吸収してしまうため、ブレーキパッドへの圧力がかからずブレーキが効かなくなる、というのがベーパーロック現象になります。
フェード現象とは?

フェード現象は、ブレーキがフェードする(=徐々に弱まる)という意味から付けられています。ブレーキを踏むことで車にかかる制動力が、フットブレーキを酷使し続けたことにより徐々に低下していく現象です。
ブレーキを踏むことで発生する制動力には、ディスクブレーキ・ドラムブレーキのどちらの仕組みの場合も、摩擦によって発生する摩擦抵抗力が利用されています。摩擦が起こると、同時に摩擦熱も発生します。ブレーキが酷使されると高温の摩擦熱が発生し続けます。摩擦熱の温度がブレーキの耐熱温度を超えてしまった結果として、分解が起こり、分解ガスの発生につながります。分解ガスがブレーキパッドとディスクローターの間に入ると、摩擦が起きづらくなり制動力が失われるため、このようにブレーキが効かない状態となることをフェード現象と言います。
ベーパーロック現象・フェード現象の原因と対策
ベーパーロック現象とフェード現象はフットブレーキを使用する時に発生すると前述しました。
次に、ベーパーロック現象・フェード現象が起きる原因や、現象が起きないように防止するための対策方法をご紹介します。
ベーパーロック現象・フェード現象の原因は
ベーパーロック現象、フェード現象の発生する原因として、双方ともに当てはまるのが、「フットブレーキによる制動力を酷使し続けたこと」です。特にAT(オートマチックトランスミッション)車のドライバーは、エンジンブレーキの活用に不慣れなためフットブレーキへの依存度が高く、フットブレーキの使い過ぎからベーパーロック現象やフェード現象が起こりやすいと言われています。
ベーパーロック現象についてはフットブレーキの酷使も原因となりますが、その他にもブレーキオイルの点検や交換を怠ったことが原因になる可能性があります。先ほども解説した通りブレーキオイルは元々吸湿性が高いため、メンテナンスの中にオイルの水抜きという工程があるのです。ブレーキオイルに水分が含まれていると大きなトラブルにつながる可能性もありますので、定期的にオイルの内容を点検して水抜きや必要な場合は交換することが大切なポイントの一つです。
フェード現象についても、フットブレーキの酷使だけが原因とは限りません。ブレーキパッドの目視点検や定期交換を怠ってしまうと、摩擦材が薄くなっているため熱耐性が弱くなり、分解が起こりやすい状態になっているかもしれません。
ブレーキオイル・ブレーキパッドは定期的に交換
上記の原因から対策を講じるのであれば、消耗部品であるブレーキオイルとブレーキパッドの点検・交換は必須です。それぞれの交換目安をご紹介します。
ブレーキオイルの交換目安は、使用開始から経過2年毎を推奨しています。ただ車の利用状況次第では、年数で測れないことがあり、もう一つの目安として走行距離が1万km~1.5万kmを超えた頃と言われています。ブレーキオイルはエンジンルームを開けると半透明なオイルタンクに入っています。色でも目視点検が可能です。黒系や緑系の色に変色している時はすでに劣化状態と考えられるため交換が必要です。
ブレーキパッドは、摩擦材の厚みが3mm以下になると交換時期です。厚みについては目視でも確認できます。また、4,000~5,000kmの走行距離毎の交換を推奨されていますので、オイルよりも交換スピードは速くなります。
ブレーキオイルとブレーキパッドの交換を整備工場に依頼するのであれば、同時に依頼したいという方は多いでしょう。同時に交換するならブレーキパッドの交換時期を目安に依頼すると良いでしょう。
フットブレーキの使用頻度を控えめに

ベーパーロック現象やフェード現象を起こさないために、フットブレーキの使用頻度を減らした運転操作に慣れておくことも有効です。
山間部で山を越えるような下り坂の場合、坂道が長く続きます。このような下り坂を走行する間、ずっとフットブレーキを使い続けて減速しようとすると、ベーパーロック現象やフェード現象が起こってブレーキが効かず危険運転になる可能性があります。フットブレーキを酷使せず、使用頻度を減らして長い下り坂を走行するために、エンジンブレーキを利用する運転操作方法をご紹介します。
まず下り坂に差し掛かる前に、シフトレバーを操作して、通常走行時の【ドライブギア】から【スピードがでないギア】へ変更し、速度を調整しましょう。低速で安定したスピードを出すためのギアは、車種によって名称が違います。車種ごとの取扱説明書を見てシフトレバー周辺の説明を読みましょう。例でいうと、2(セカンド)ギア、L(ロー)ギア、B(エンジンブレーキ)ギアなどがあります。
ブレーキを使用する順は、シフトレバーでギアを調整してエンジンブレーキ(エンジンへの燃料供給を止めることで速度を落とす)を使い、その後にブレーキペダルを踏んでフットブレーキです。山間部を走行する機会がある方は、特に減速する時の運転操作として覚えておくと良いでしょう。
その他の運転中に起こる現象について
ベーパーロック現象やフェード現象について詳しくご紹介しましたが、この他にもブレーキに関連して車で起こる現象がいくつかありますので、こちらでご紹介します。
ハイドロプレーニング現象

ハイドロプレーニング現象とは、【hydro:水が】【planing:平らになる・滑る】から付けられた車で走行中に起こる現象のことです。
雨水などで濡れた路面を走行していると、タイヤの溝に路面の水が入る、排水されるを繰り返して走行することになります。排水に問題がなければ、例え濡れた路面であってもタイヤの溝が路面の引っ掛かりを掴み、安全に走行できます。しかし、一定以上に速いスピードで走ってしまうと排水が追い付かず、路面とタイヤの間に水膜が張って車が浮き上がったような状態になり、ハンドルの操作がきかず危険な運転になってしまうのです。
スピードだけでなく、深い水たまりが続いてタイヤが水の中から抜け出せない道路でも、走行を続けると排水ができないため、ハイドロプレーニング現象が起こりやすくなります。雨の日に運転をする時は、まずスピードを出し過ぎないように気を付けましょう。
エア噛み
前述のベーパーロック現象の内容で解説したように、ブレーキオイルに気泡(空気)が混ざると、エアポケットに圧力が吸収されてしまうため、ブレーキが効かなくなるとご紹介しました。車にはいくつか油圧システムを利用する仕組みがあるのですが、そのオイル内に気泡が発生したり、空気が混入していることで油圧が伝わらない状態になっている現象を【エア噛み】といいます。
エア噛みの状態になっていると、ブレーキペダルを踏み込んでもブレーキの感覚がなく、ペダルがふわふわするようにドライバーは感じるため不安を感じる走行状態になります。
ブレーキジャダー現象
ブレーキジャダー現象とは、ブレーキを掛けようとした時にハンドルやブレーキペダル、車体本体がブルブルやガクガクと振動しているように感じる現象のことです。
ブレーキジャダー現象は、ブレーキディスクの偏摩耗やブレーキパッドが劣化しているのに交換が出来ていないことで、摩擦が付均一になり起こる現象となっています。振動やがたつきがあった時は、速やかに点検・交換を依頼しましょう。
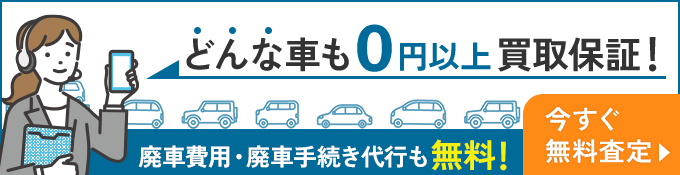
まとめ
こちらの記事では、ベーパーロック現象とフェード現象の違いや、なぜこのような現象が起こるのかという原因について解説しました。
ベーパーロック現象はオイル内に気泡が発生することで、油圧が効かなくなりブレーキがかからない状態のことです。フェード現象はブレーキパッドが高温の摩擦熱によって分解してしまい、ディスクローターに対して摩擦抵抗がないためブレーキが効かない状態のことです。
どちらも走行中に起こると大きな事故に繋がる可能性が高く、大変危険な現象となっています。部品点検・交換を行っておくことや、運転操作にエンジンブレーキを取り入れるなどの対策を覚えておかれることをおすすめします。